「最初はハマってたのに、今は開いてないアプリ」
誰にでも、ひとつや二つはあるはず。
勉強アプリ、歩数アプリ、ダイエットアプリ、
どれも最初は楽しくて続いていたのに、
だんだん飽きて、気づけば通知を無視している…。
──それは、人間の“慣れ”が原因です。
人は同じ刺激が続くと、次第に反応が薄れてしまう。
だから、うまく続けてもらうためには「少しの変化」を設計する必要があるんです。
「変化」がないと脳は反応しなくなる
心理学では、人が同じ刺激に慣れることを「馴化(じゅんか)」と呼びます。
たとえば:
最初の1日目はワクワク
3日目はまあまあ
7日目には「いつものやつね」
つまり、どんなに楽しい仕組みでも、同じままだと飽きる。
だからゲームやサービスでは、
「少しずつ変わる」「時々違う」という仕掛けを入れて、
人の興味を保ち続けているんです。
ゲームの世界に学ぶ「飽きさせない工夫」
多くの人気ゲームには、次のような“変化”のパターンがあります。
| 工夫 | 内容 | 例 |
| 🎁 ランダム性 | 何が出るか分からない楽しみ | ガチャ・ルーレット・毎日のボーナス |
| 🌈 段階的変化 | 少しずつ強くなる・広がる | レベルアップ・新マップ・新敵出現 |
| 📅 限定要素 | 「今だけ」「今日だけ」 | 期間イベント・曜日ミッション |
| 💬 演出変化 | 音・色・アニメーションの変化 | クリア演出・ログイン画面の変化 |
こうした変化があることで、
「昨日と同じことをしているのに、新しい体験」に感じられるようになるんです。
ゲームじゃなくても“飽きさせない設計”は使われている
実はこの工夫、ゲーム以外のアプリやサービスにも広く使われています。
健康アプリ:毎日の目標値やミッションが少しずつ変わる
ポイントアプリ:ログインごとにボーナス内容が変わる
教育アプリ:復習の出題パターンが変化する
お店のアプリ:曜日ごとに特典が違う
こうした“ちょっとした変化”が、ユーザーに新鮮さを与え、飽きを防いでいます。
「予測できそうでできない」が一番楽しい
人は“完全なランダム”よりも、
「なんとなく予想できるけど、ちょっとズレる」くらいが一番楽しいんです。
たとえば:
「明日はどんなボーナスかな?」
「次のレベルでは何が起こるんだろう?」
こうした“少しの不確実さ”があることで、
脳はワクワクを感じ続けます。
ゲームデザインでは、これを「ランダム報酬」や「変動スケジュール」と呼びますが、
日常的には「サプライズの演出」と言っていいでしょう。
飽きない仕組み=“変化のリズム”を作ること
大切なのは、常に変えることではなく、リズムを作ること。
たとえば:
「毎週金曜に新しいクエストが出る」
「毎月1日は特別ログインボーナス」
「連続10日ログインで限定アイテム」
人は“予想できる変化”にも安心感を感じます。
だから、「決まった変化」と「ランダムな変化」を組み合わせるのが理想的。
まとめ
同じことの繰り返しは飽きる
少しの変化で新鮮さを感じる
ランダム・限定・段階的変化が飽きを防ぐ
ゲームもサービスも“変化のリズム”を設計している
こうして見ると、「続けること」と「飽きないこと」は別の話のようで、
実は同じ“体験設計”の両輪なんです。
次の第9回では、
「やりすぎ注意!失敗する“続けさせる仕組み”」をテーマに、
“押しつけすぎた仕組み”がなぜユーザーの心を離してしまうのか、
その危険性とバランスの取り方をお話しします。
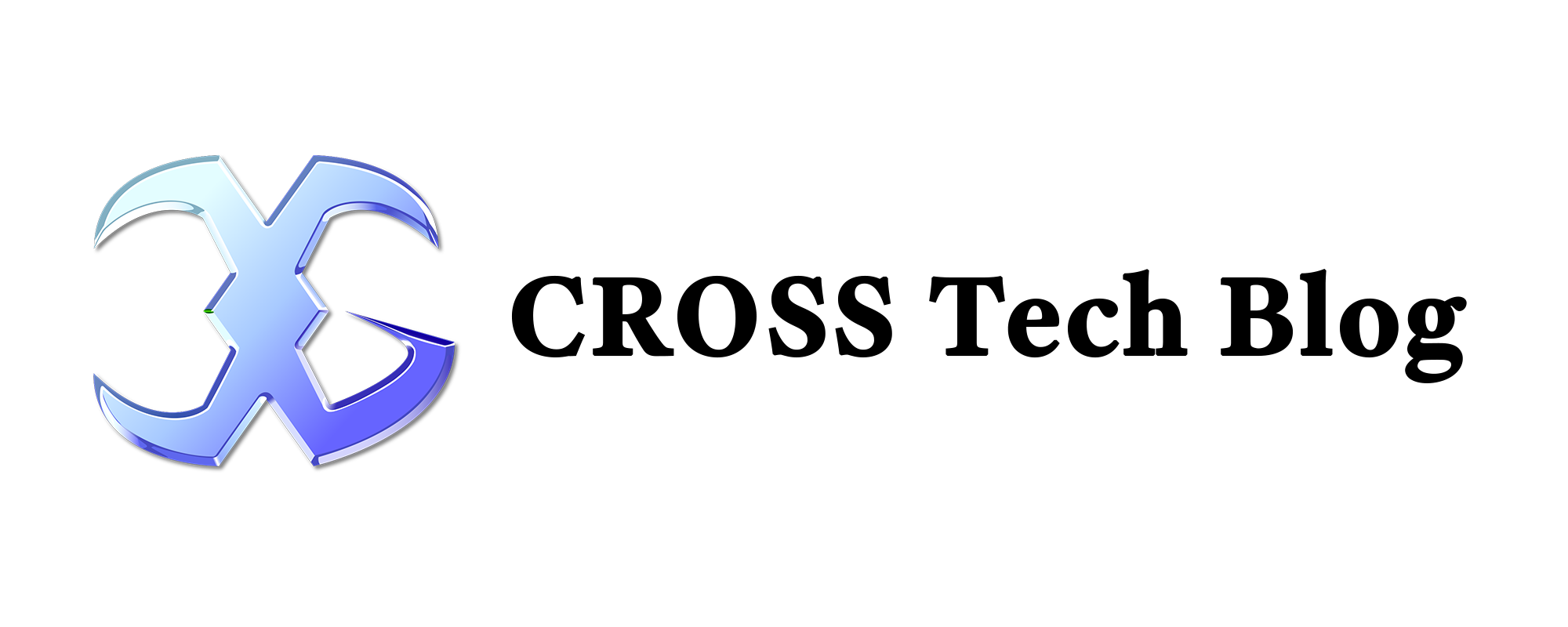
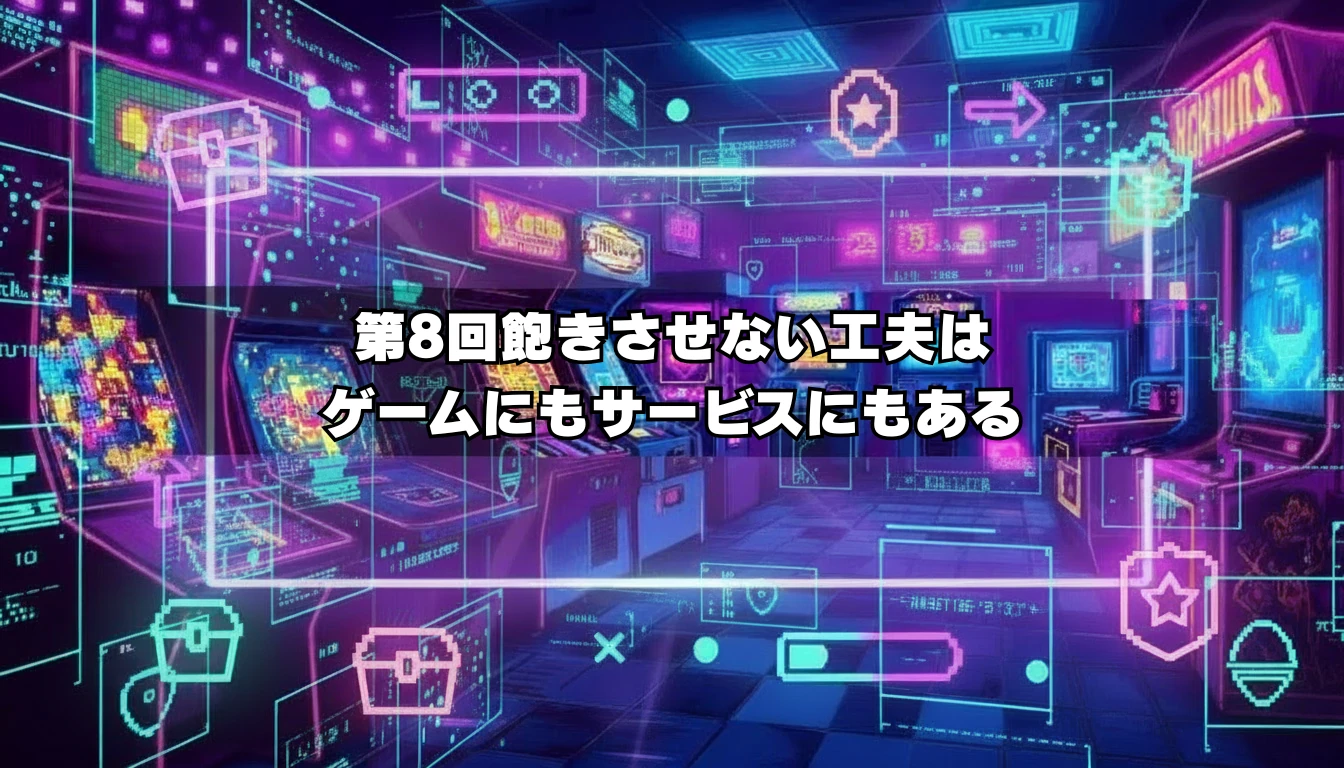


コメント