朝起きてスマホを見る。
コンビニでいつものコーヒーを買う。
帰り道で同じ曲を聴く。
最初は「意識して」やっていたのに、
気づけば「やるのが当たり前」になっている。
これが、習慣の力です。
でも実は、「気づいたら続いていた」状態には、
ちゃんと“仕組み”があるんです。
習慣は「行動のハードル」を下げることから始まる
人はめんどくさいことを避けたがります。
でも、少しだけラクになると行動しやすくなる。
たとえば:
歯ブラシをコップの中に出しておくと、磨くのが面倒じゃなくなる
アプリのアイコンをホーム画面の1ページ目に置くと、起動しやすい
「1日1分だけやろう」と決めると、続けやすい
つまり、“始めるまでの障害を小さくする”ことが最初の工夫なんです。
習慣化には「きっかけ」が必要
「続けよう」と思っても、きっかけがなければ始まりません。
ゲームのログイン通知や、
お店の「ポイント2倍デー」などは、
実はこの“きっかけ”を意図的に作っています。
きっかけ → 行動 → ごほうび
このサイクルが回り始めると、
人は自動的に繰り返すようになるんです。
「ごほうび」は“脳が覚えるサイン”
行動したあとに“ちょっとしたごほうび”があると、
脳は「これをやると良いことがある」と学習します。
たとえば、
歩数アプリでバッジがもらえる
勉強アプリでレベルアップする
SNSで「いいね」がつく
これらはすべて、“行動を強化するごほうび”。
大げさな報酬でなくても、小さな達成感で十分なんです。
「やらなきゃ」より「気づいたら」続く設計へ
習慣のゴールは、「頑張らなくてもできる状態」。
たとえば:
朝のニュースアプリを開くのがルーティンになる
日記アプリを寝る前に開くのが自然になる
スマホゲームを1日1回立ち上げるのが習慣になる
こうした状態は、意志ではなく仕組みで作られています。
アプリ開発者やデザイナーは、
「人が自然と繰り返す導線」をデザインしているんです。
「続けやすい仕組み」は、誰でも作れる
習慣づくりのコツをまとめると:
工夫のポイント
1️⃣ ハードルを下げる
2️⃣ きっかけを作る
3️⃣ ごほうびを用意する
4️⃣ 結果が見える化されている
5️⃣ 続けたくなる演出
これらを組み合わせれば、
アプリでもサービスでも「自然と続けられる」設計が可能です。
まとめ
人は“意志が強いから”続けられるのではなく、
“続けやすくなるように工夫されている”から続けられる。
そして、その工夫こそが、
次の章で出てくる「ゲームの仕組みを応用したデザイン」につながっていきます。
次の第7回では、
「なぜ人は“ごほうび”を欲しがるのか?」を掘り下げます。
ちょっとしたごほうびが、なぜあんなにも行動を変えるのか?
心理の仕組みを、身近な例で解き明かしていきます。
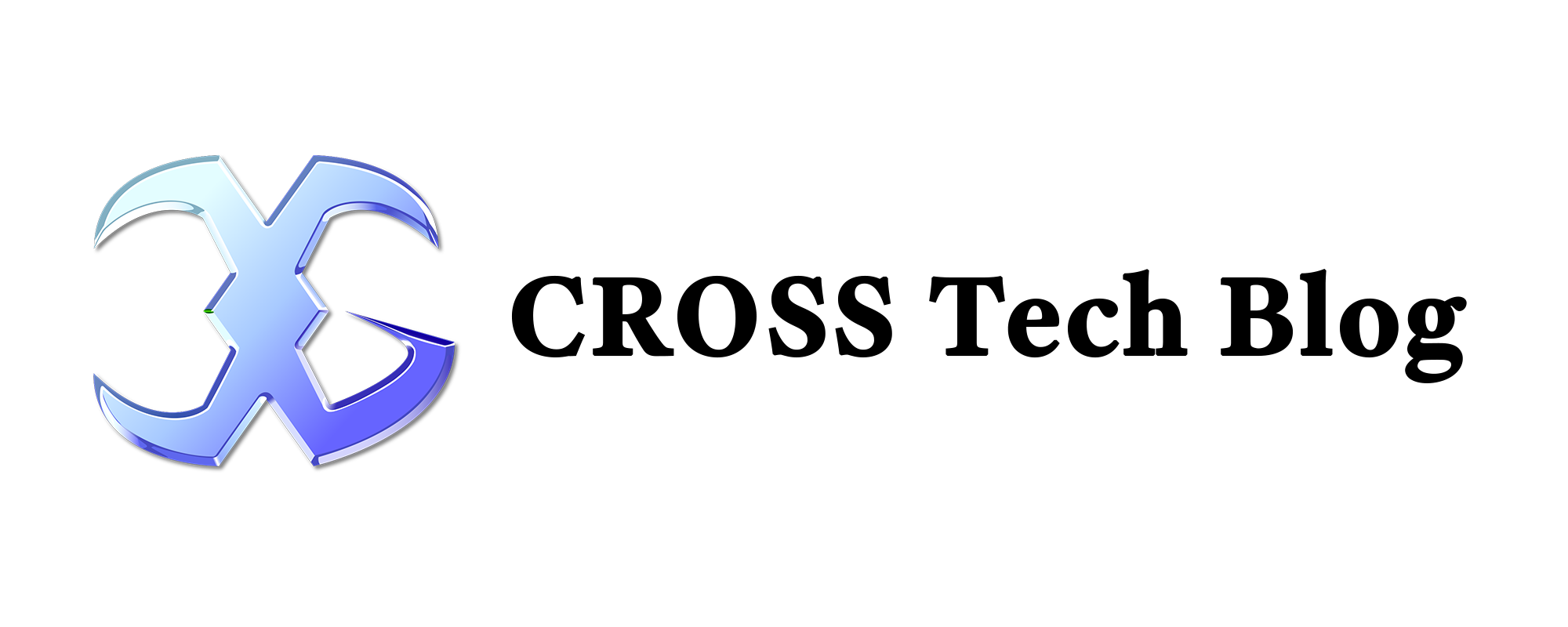
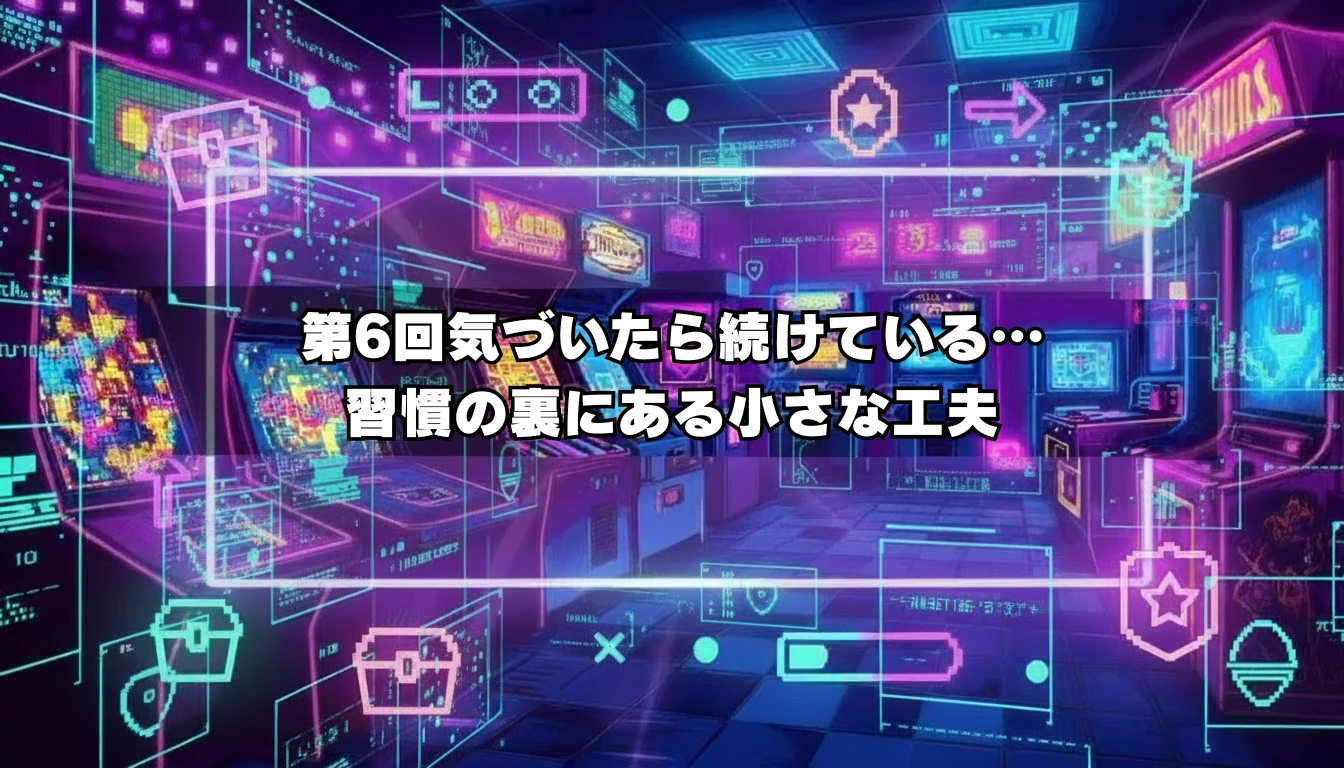


コメント