歩数アプリで「今日の目標達成!」と出る。
ゲームで「レベルアップ!」の音が鳴る。
ポイントアプリで「+1ポイント」の通知が来る。
──たったそれだけのことなのに、なぜか嬉しい。
しかも、またやりたくなる。
人はどうしてこんなにも“ごほうび”に弱いのでしょう?
実はそこには、脳の「報酬回路」という仕組みが関係しています。
ごほうびは「脳のスイッチ」を押す
人の脳は、ごほうびを得るとドーパミンという物質を出します。
これは「幸せホルモン」とも呼ばれ、
「またやりたい」「次も欲しい」と思わせる働きがあります。
つまり、ごほうびは気持ちのガソリンなんです。
面白いのは、
「ごほうびをもらう時」よりも
「もらえるかも!と思う時」の方がドーパミンが多く出ること。
だから、
ガチャを引く瞬間
くじをめくる瞬間
“あと少しで達成!”の時
がいちばんワクワクするんです。
ごほうびは“結果”より“期待”が楽しい
この「もらえるかも!」という期待の時間こそが、
人を行動に向かわせる大きな力。
たとえば:
歩数アプリの“今日のボーナス”
ゲームの“次のレベルアップ”
スタンプカードの“あと1回で特典”
これらはすべて、「期待を続けさせるデザイン」。
つまり、ごほうびの本質は“結果”ではなく“期待の持続”なんです。
ごほうびの大きさより「頻度」が大事
意外かもしれませんが、
ごほうびは“大きいほど良い”わけではありません。
1か月後に1万円もらえる
よりも
毎日100円もらえる
方が、続けたくなる人は多い。
これは「即時報酬」と呼ばれ、
短いサイクルで嬉しさを感じる設計が、行動を継続させるんです。
ゲームの「ログインボーナス」や「デイリーミッション」も、
まさにこの考え方を取り入れています。
ごほうびには“種類”がある
ごほうびには、実は2つのタイプがあります。
種類
🎁 外的ごほうび
🌟 内的ごほうび
たとえば、
「毎日続けた自分を誇らしく思える」
「努力が見えるグラフが増えて嬉しい」
──こうした“内的なごほうび”も、実はとても強力です。
アプリやゲームの設計では、
外的報酬 → 内的報酬へと移行させることが、長期的な継続につながります。
ごほうびが「習慣化」のトリガーになる
ごほうびがあると、行動が“楽しい経験”として脳に記録されます。
すると次からは、意識しなくても「またやろう」と思えるようになる。
つまり、
ごほうび → 行動 → ごほうび → 行動…
というサイクルが、習慣化を生み出すのです。
まとめ
ごほうびは「脳のガソリン」
“もらえるかも”の期待が行動を生む
小さな報酬をこまめに与える方が効果的
外的報酬 → 内的報酬に育てていくのが理想
ごほうびの設計は、
「人を動かす仕組み」の中で最も強力な要素のひとつです。
次の第8回では、
「飽きさせない工夫はゲームにもサービスにもある」をテーマに、
“ごほうびを続けて感じてもらう”ための「変化のデザイン」を紹介します。
毎回同じことをしても退屈しないようにする――
そこにも、ちゃんとした仕組みがあるんです。
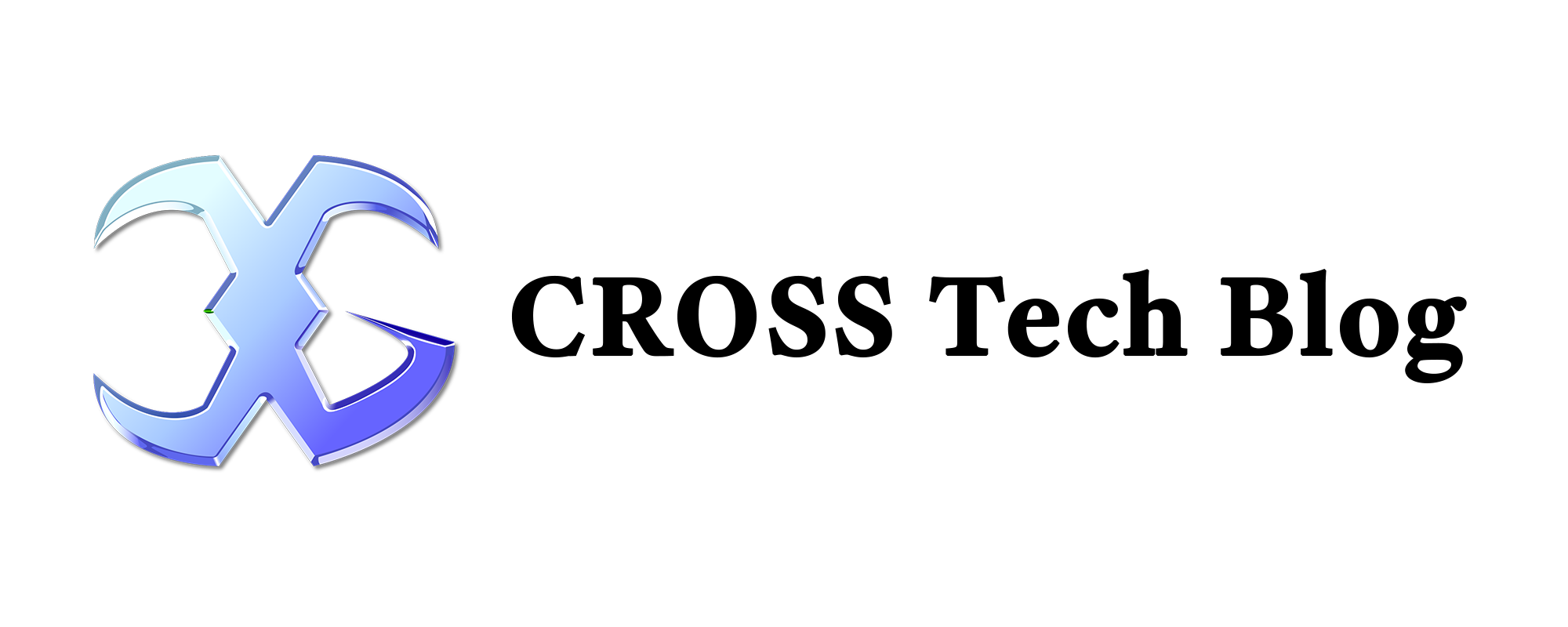
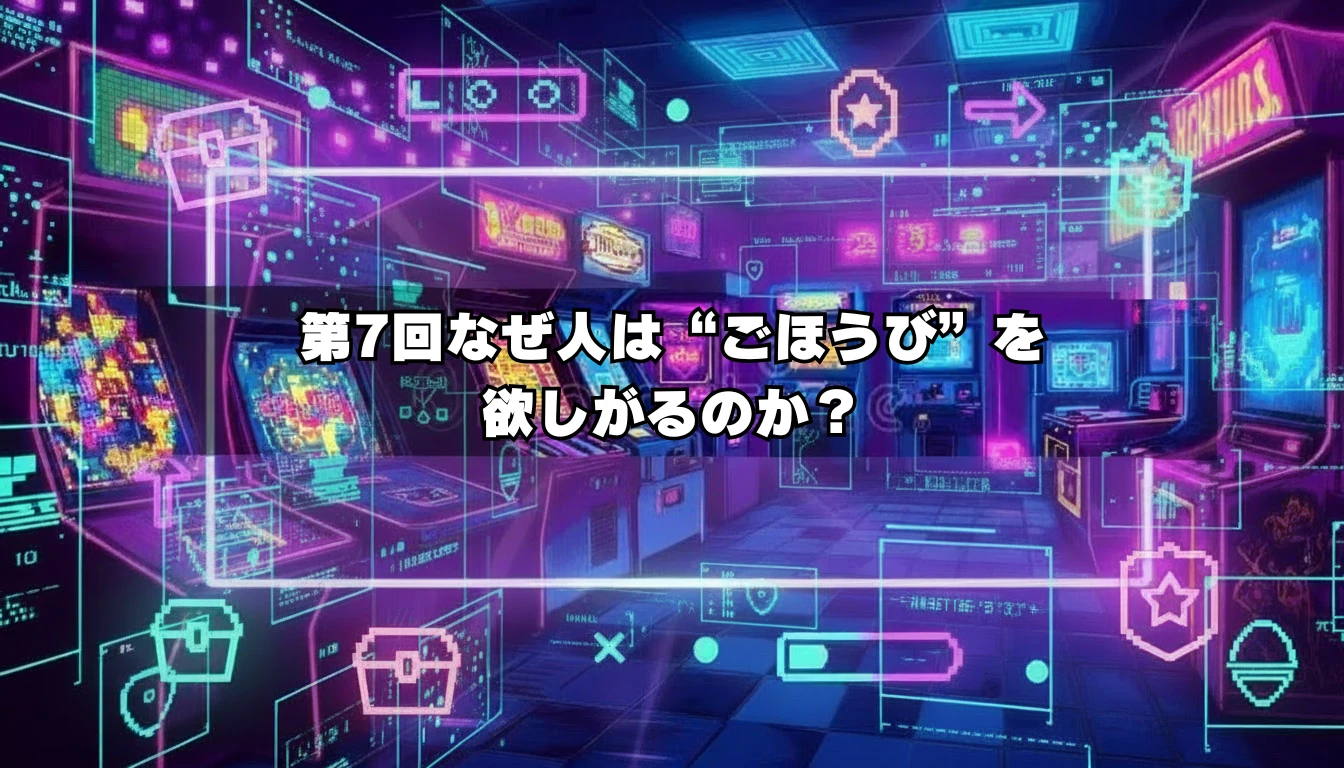


コメント