コンビニのスタンプカード、
SNSの「いいね」ボタン、
健康アプリの連続記録、
ポイントが貯まる仕組み…。
普段、当たり前のように使っているサービスの中には、
「続けたくなる工夫」がたくさん隠れています。
何気なく触れていた仕組みも、
その“意図”を知ると、少し見方が変わってきます。
「なんとなく使ってる」の裏にあるデザインの意図
これまで紹介してきたように、
私たちが“なんとなく”続けている行動の多くは、
しっかりとした設計思想に支えられています。
ログインボーナス → 「小さなごほうび」で毎日をつなぐ
スタンプカード → 「達成感」で習慣を作る
通知や演出 → 「飽きさせない変化」を生む
ごほうび設計 → 「モチベーションの波」を支える
こうした仕組みは、単なる“おまけ”ではなく、
人の心理を理解した「設計の力」なんです。
たとえば、あなたの1日の中にもある
朝、歩数アプリを開く。
昼、SNSの通知を見る。
夜、動画アプリで「今日のおすすめ」をチェックする。
実はそのどれもが、
「続けたくなる」「開きたくなる」ように
緻密にデザインされています。
それを知っているだけで、
「なぜ自分はこれを続けているんだろう?」と
ちょっと立ち止まって考えるようになります。
そして――
その“気づき”が、
「自分が作るサービス」にも活かせる視点になるんです。
「なるほど」と思うことが、“作る人”への第一歩
たとえば、もしあなたが:
仕事でアプリやサービスを企画している
店舗でお客さんに長く通ってもらいたい
学習や健康アプリをより続けやすくしたい
そんな立場にあるなら、
「なぜこの仕組みは続けられるのか?」という視点は
とても強力なヒントになります。
大切なのは、特別なテクニックではなく、
「人はどんなときにうれしいと感じるか」を理解すること。
それを応用すれば、
どんなサービスも“ちょっと楽しい”ものに変えられます。
そして気づく、「楽しさ」は設計できる
多くの人が「楽しさ」は偶然の産物だと思っています。
でも実は、楽しさは“設計できる”ものなんです。
それは、ゲームでも、
学習アプリでも、
カフェのスタンプカードでも。
どんな分野でも、
人の行動を“前向きに変える仕組み”を設計できる。
この視点を持てば、
「ただのサービス」も「ちょっとワクワクする体験」になります。
まとめ
日常の中には“続けたくなる仕組み”がたくさんある
その仕組みは「心理+デザイン」でできている
「なるほど」と気づくことで、自分も“作る側”になれる
楽しさは偶然ではなく、“設計できる”
ここまでの第1回から第10回では、
「続ける仕組み」がどのように日常に溶け込んでいるかを見てきました。
第11回からは、いよいよ本格的に、
「人が動きたくなる設計」=“ゲーム”の考え方を
やさしく分解していきます。
次回は――
「ゲームが楽しい理由を科学する」
「楽しい」とは何か?
「報酬」「挑戦」「達成感」はどう関係するのか?
ゲームデザインの裏にある“心理の仕組み”を
一緒にのぞいていきましょう。
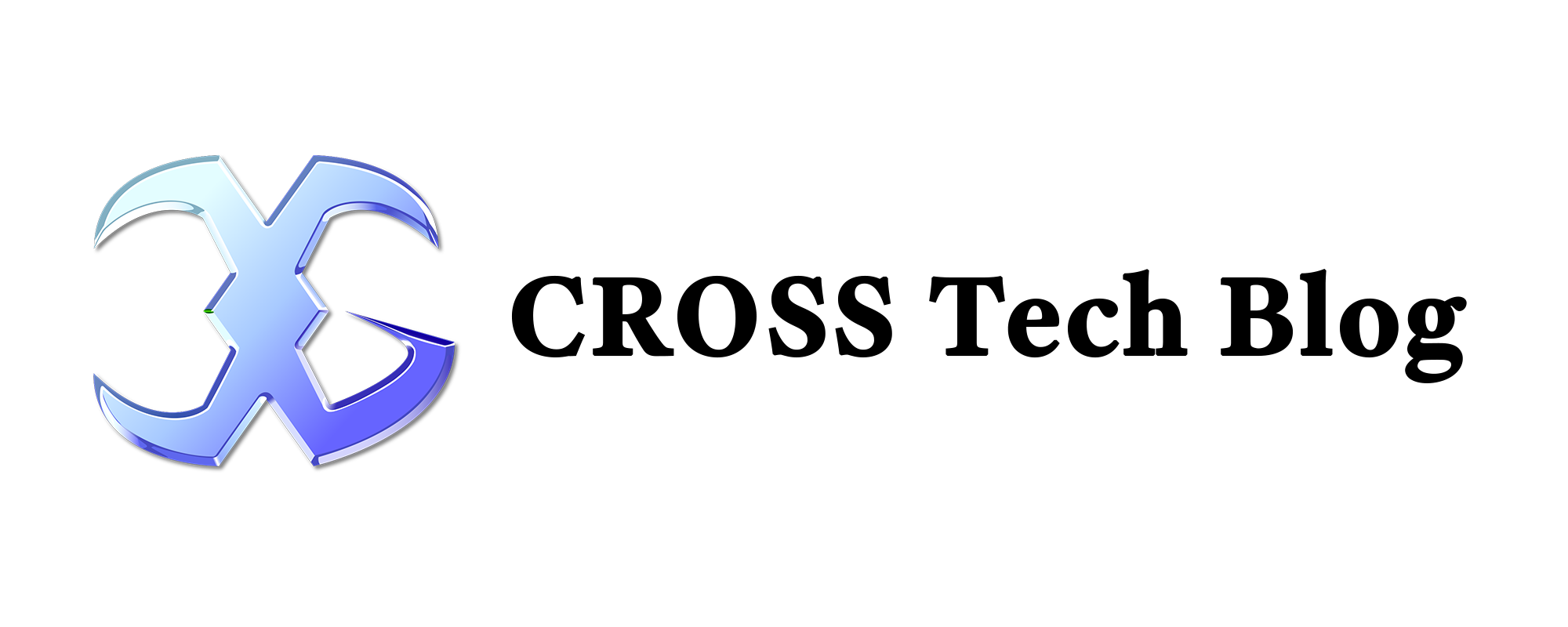



コメント