最近のアプリやサービスを見ていると、
「ゲームっぽいな」と感じるものが増えていませんか?
勉強アプリで「レベルアップ」
歩数アプリで「1日ミッション達成!」
クレジットカードアプリで「ランクアップ」
どれもゲームではないのに、まるでRPGのような仕組みが入っています。
では、なぜこうした“ゲームみたいなデザイン”が増えているのでしょうか?
「やらなきゃ」より「やりたくなる」に変えるため
人は「やらなきゃ」と思っていることほど続けづらいもの。
でも、「ちょっと楽しい」「あと少しで達成できそう」と思えると、行動が続きやすくなります。
たとえば…
家計簿アプリ → 使うたびに「記録日数」が伸びていく
語学アプリ → 毎日学ぶと「連続日数」がカウントされる
どちらも、“続けること自体が気持ちいい” 仕組みになっています。
「進んでいる感」を見せる工夫
人間は「成果が見える」とうれしい生き物です。
スタンプがたまる、バーが伸びる、レベルが上がる――。
数字やゲージで「今どこまで来たか」が見えるだけで、自然と次を目指したくなります。
これはゲームが得意としてきた演出。
でも今では、アプリやサービスでも当たり前に使われています。
「少しずつ達成できる」からやめにくい
ゲームって、「ラスボスを倒す」までの道のりに、たくさんの“小さな目標”がありますよね。
この「小さなゴール」が、長く続けるコツです。
同じように、健康アプリも「今日は5000歩」「明日は6000歩」と段階的に目標を示すことで、
「少しずつ頑張れる」仕組みを作っています。
まとめ
「ゲームっぽい仕組み」は、
ただ楽しくするためではなく、
“続けやすくする”ための工夫 なんです。
ゲームは何十年もかけて「人が夢中になる仕組み」を磨いてきました。
その知恵を、いろんなサービスが取り入れている――
だからこそ、ゲームじゃなくても“ゲームみたい”な仕組みがあるのです。
次回は、「“楽しい”と“続けられる”はちょっと違う?」というお話。
なぜ「楽しいだけ」では続かないのか、
“続ける力”を生む仕組みについて見ていきます。
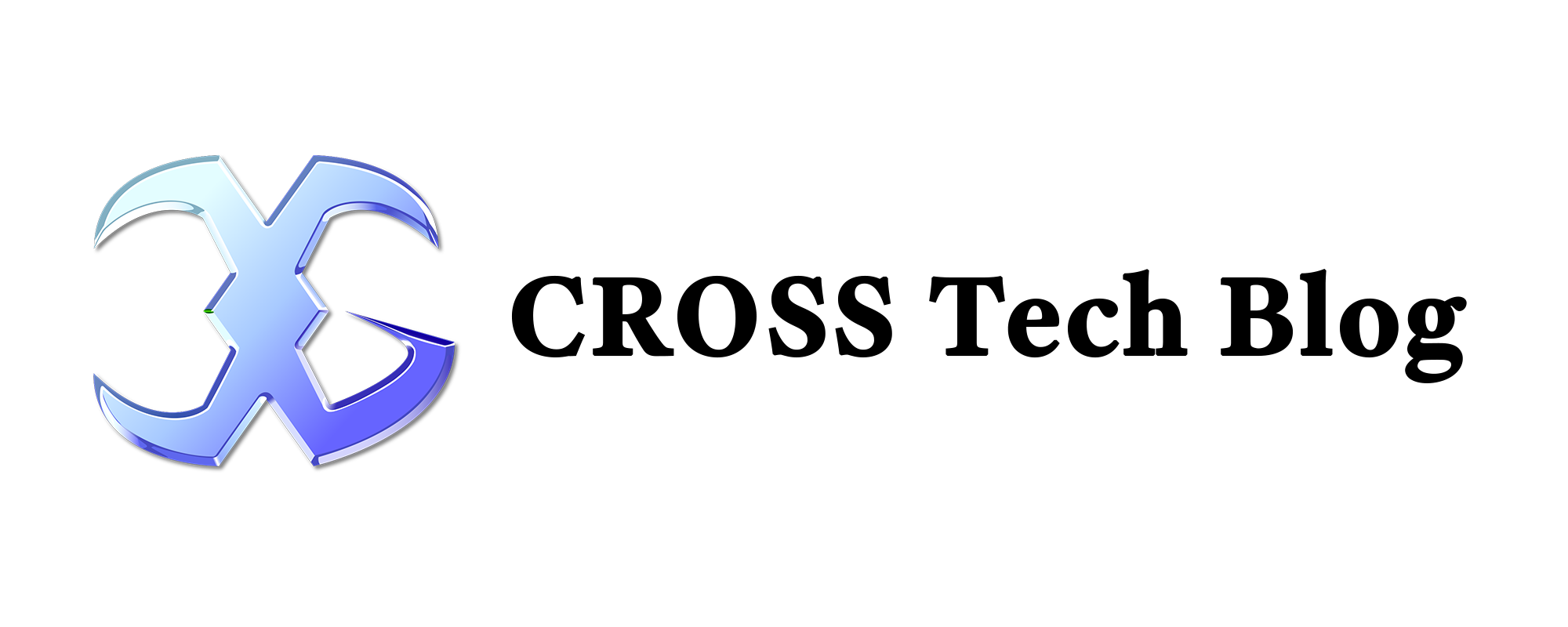
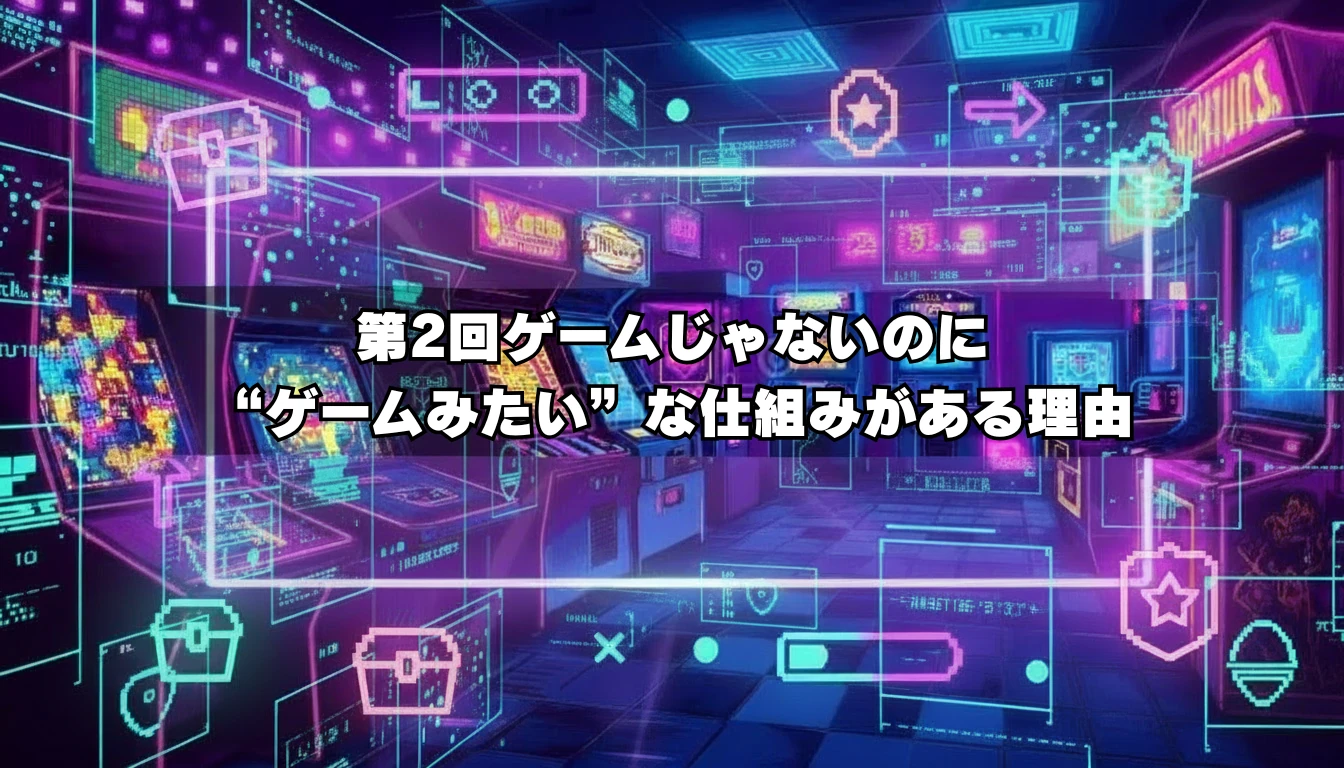


コメント