最初は「楽しい!」と思って毎日使っていたのに、
気づいたら「なんか疲れる…」と感じてやめてしまった。
そんな経験、ありませんか?
実はこれ、
「続けさせよう」としすぎた設計の失敗なんです。
どんなに良い仕組みも、
“やりすぎ”になると人の気持ちを遠ざけてしまうんです。
「義務感」になった瞬間、楽しくなくなる
人は、“やらなきゃ”という気持ちになると、
どんな楽しいことでも急に重たく感じます。
たとえば:
「毎日ログインしないと損する」
「途切れたら全部リセット」
「通知がうるさいくらい届く」
こうした仕組みは、最初はモチベーションになりますが、
次第に「やらされている」感が強くなってしまう。
続けることが楽しみ → 義務に変わると、
人は自然と離れていきます。
“報酬の罠”にハマると、やめた瞬間に冷める
「毎日ポイント」「ログインボーナス」「ランキング」など、
報酬を強く押し出す仕組みは、短期的には効果があります。
でも――
報酬がなくなった瞬間にやめてしまう人が多いんです。
これは「外的報酬に頼りすぎた設計」の典型例。
本来、人が続ける理由は、
「楽しい」「上達してる」「自分のペースでできる」などの内側の満足感。
それを報酬で上書きしてしまうと、
“ごほうびがない=意味がない”と感じてしまうんです。
通知・ランキング・ミッションの“過剰刺激”
アプリやゲームの中には、
「通知が多すぎる」
「ランキングが常にプレッシャー」
「ミッションが多すぎて追いつけない」
という状態に陥るものもあります。
これらは一見「やる気を引き出す」ように見えますが、
ユーザーにとってはストレスの原因になります。
人は「やりたいこと」よりも「できなかったこと」に敏感。
やり残しが多いと「自分はダメだ」と感じ、
アプリ自体を避けるようになるんです。
「続けさせる」より「寄り添う」設計へ
成功しているサービスは、
“押しつける”のではなく、“支える”形で継続を促しています。
たとえば:
「今日はお休みも大事!」 と伝える健康アプリ
「続けてるあなた、すごいね!」 と褒める学習アプリ
「目標をリセットして再スタートできる」 柔軟な仕組み
続けられない日があっても責めない設計。
それが、結果的に長く愛される仕組みにつながります。
“やめない仕組み”ではなく、“戻ってこれる仕組み”
本当に良い仕組みは、
「離れにくい」ものではなく、
「いつでも戻れる」もの。
人は一度離れても、
“安心して再開できる”とわかっていれば、また戻ってきます。
だからこそ、
「休んでもOK」「再開しやすい設計」がとても大切なんです。
まとめ
義務感はモチベーションを壊す
報酬の与えすぎは逆効果になる
通知やランキングの押しつけは疲れを生む
「またやりたくなる」「戻りやすい」設計が理想
人を“動かす仕組み”は、力強くすることよりも、
優しく支えることで、はるかに長く続くんです。
第1章の締めくくりとなる第10回では、
これまでの「続ける」「飽きない」「ごほうび」「習慣」をまとめて、
“日常を少し楽しく変える視点”としてお届けします。
タイトルは――
「『なるほど!』とわかると日常が変わる」
お楽しみに。
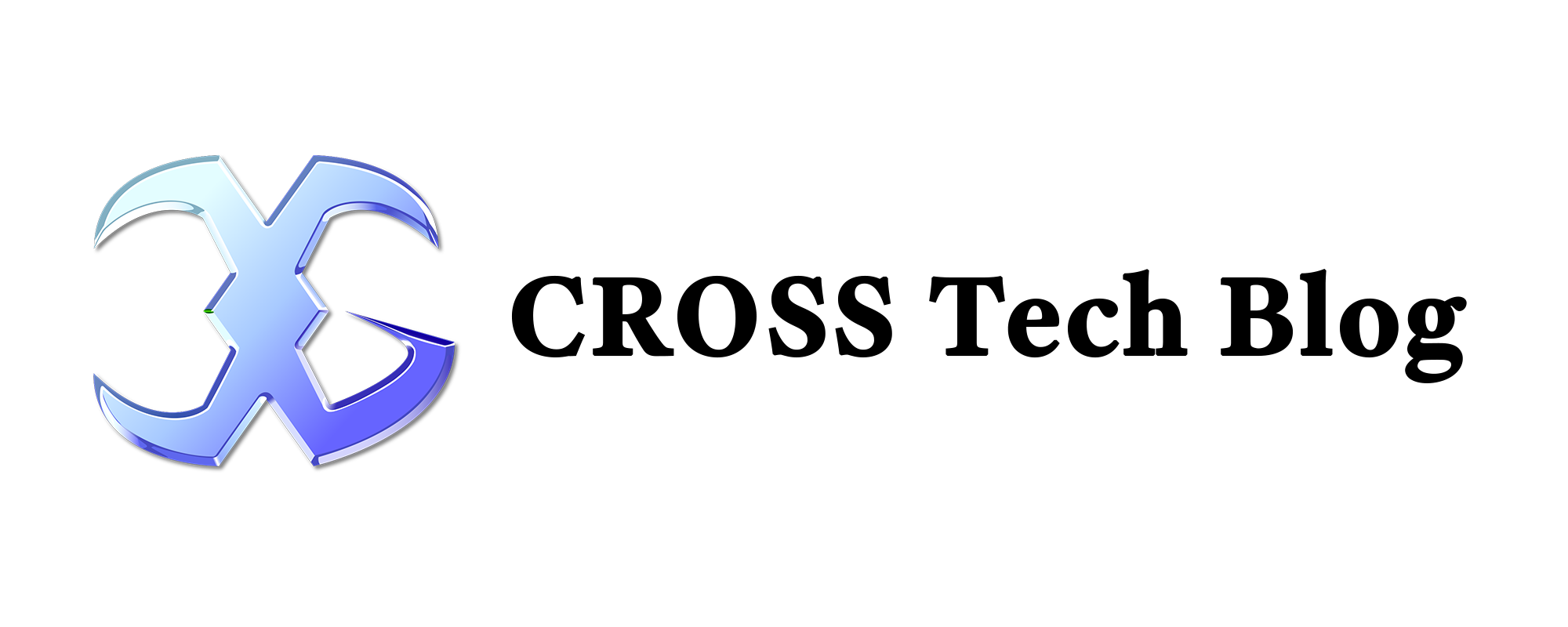



コメント