スマホゲームを遊んでいて、
「あと少しでクリアできそうなのに、スタミナが切れた…」
そんな経験はありませんか?
制限があると本来なら“やめる”方向に働きそうですが、
多くの人は「次に遊べるタイミング」を楽しみに待つようになります。
つまり、スタミナ制は制限なのに、継続を生む仕組みなんです。
心理学でいう「希少性」と「ツァイガルニク効果」
人が制限に惹かれるのは、心理的な理由があります。
1️⃣ 希少性の法則(Scarcity Principle)
「手に入りにくいものほど欲しくなる」
→ 無制限に遊べるより、「限られたチャンスしかない方が価値を感じる」
2️⃣ ツァイガルニク効果(Zeigarnik Effect)
「中断された行動ほど、頭の中に残り続ける」
→ スタミナが切れて中断されると、「続きが気になる」状態になる
つまりスタミナ制は、
“人の脳が気にしてしまう仕組み”をうまく利用しているんです。
「待つこと」が行動を強化する
スタミナ制のもう一つの面白さは、待ち時間そのものがモチベーションになること。
たとえば:
「あと10分でスタミナ回復!」
「寝る前に回復するから、朝またやろう」
このように、プレイを生活のリズムに組み込む効果があります。
毎日の“習慣化”を自然に促すデザインなんです。
制限が「やる気スイッチ」になる理由
制限があると、プレイヤーは「どうすれば効率的に遊べるか」を考え始めます。
たとえば:
「スタミナを無駄にしないよう、朝と夜にログインしよう」
「スタミナ回復アイテムを貯めておこう」
「次のイベントに備えてスタミナを温存しよう」
こうして行動の計画性と継続性が自然に生まれる。
“自由に遊べる”よりも、“限られているからこそ考える”わけです。
ゲーム以外のスタミナ制の応用
実は「スタミナ制的な制限」は、
日常のサービスにも多く応用されています。
| 分野 | 例 | 制限の目的 |
| 学習アプリ | 1日10問まで | 毎日続ける習慣化 |
| 健康アプリ | ステップ目標の上限 | 無理せず継続させる |
| ECサイト | 期間限定クーポン | 行動のきっかけ作り |
| サブスク | 無料プランの回数制限 | 有料化への導線 |
“やりすぎ防止”と“次への期待”を両立する、
まさに「持続的エンゲージメント」の設計です。
やりすぎると「不自由さ」に変わる
とはいえ、制限は諸刃の剣。
スタミナの回復が遅すぎる
プレイ時間を強制的に止める
回復アイテムを課金でしか得られない
こうした設計は、「自由を奪う不快感」に変わってしまいます。
大事なのは、ユーザーが“制限を自分でコントロールできる感覚”を持てること。
たとえば:
広告視聴や行動報酬で回復できる
スタミナを貯めておける
イベントごとに上限が変わる
このように、制限の中に選択肢を与えることが重要です。
まとめ
制限は「希少性」と「中断効果」を生む
待つ時間が“次の行動”への動機になる
無制限より、少し足りないくらいがちょうどいい
ただし、プレイヤーが「選べる余地」が必要
次回は第19回「イベント:期間限定が燃える心理」。
“いましか手に入らない”がなぜ人を動かすのか。
その裏にある心理メカニズムと応用法を探ります。
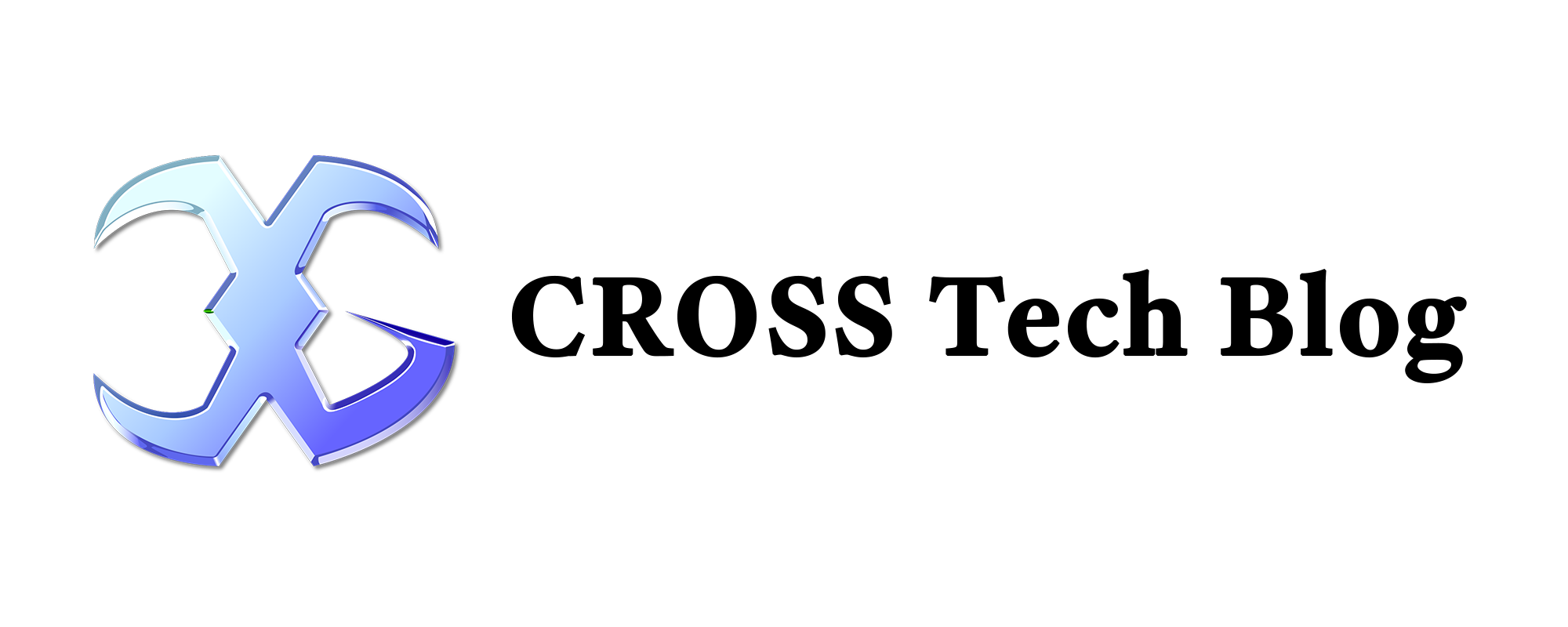
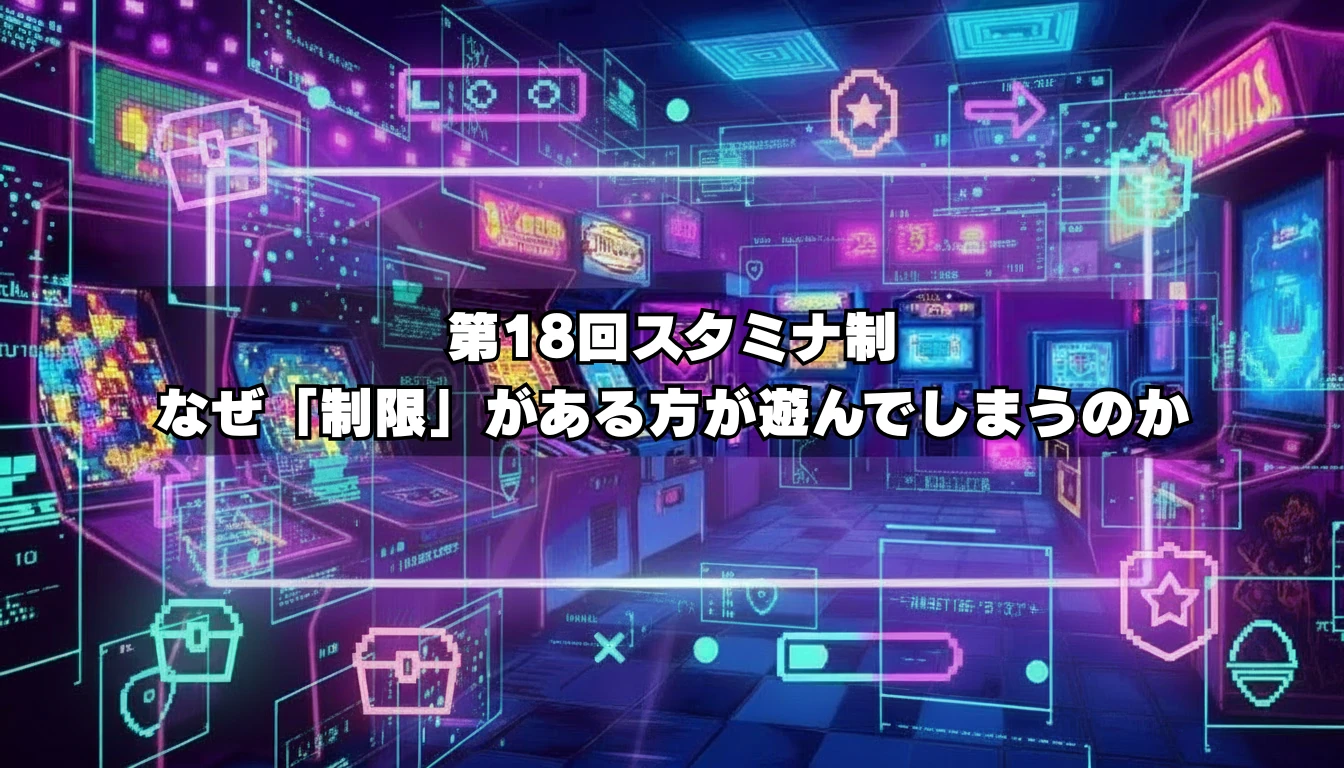


コメント