スマホゲームでおなじみの「ガチャ」。
ボタンを押すとアイテムが出てくる――たったそれだけなのに、
なぜか何度も引きたくなる。
この“ドキドキ感”の正体は、「偶然の報酬」にあります。
結果が予測できないからこそ、当たったときの喜びが何倍にもふくらむのです。
まるで宝くじやクレーンゲームと同じで、
「もしかしたら次は当たるかも」という期待が、行動を繰り返させます。
心理学でいう「変動報酬スケジュール」
心理学者B.F.スキナーの行動実験でわかったのが、
「報酬のタイミングがランダムなほうが、人はやめにくい」という法則です。
これは「変動報酬スケジュール(Variable Ratio Schedule)」と呼ばれる仕組みで、
パチンコ・スロット・ガチャ・SNSの“いいね”などにも応用されています。
たとえば:
10回やって1回当たるよりも、いつ当たるかわからない方がハマりやすい
当たらない時間が長いほど、当たったときの喜びが大きくなる
つまり、人は「不確実な報酬」に魅了されるのです。
「予測できない楽しさ」が生むワクワク
ガチャは単なる“くじ引き”ではありません。
実は、「期待 → 結果 → 感情の爆発」という一連の流れを体験させるデザインです。
回す前:期待と緊張(ドキドキ)
出る瞬間:集中と感情の高まり
当たった後:達成感と快感
この“感情の波”こそが、人を引きつける要因です。
つまり、ガチャは「報酬」よりも「感情の体験」を売っているんです。
ガチャのような仕組みは日常にもある
実は、ガチャ的な「偶然の報酬」は、
ゲーム以外の世界にもたくさん使われています。
コンビニのくじキャンペーン:「くじを引いて当たれば無料」
アプリのログインボーナス(ランダム報酬)
SNSの“いいね”通知:いつ届くかわからない快感
ECサイトの「ランダム福袋」
すべて「次こそは!」という期待を利用した、
“変動報酬”の応用例なんです。
うまく使えば「継続のスパイス」になる
ガチャ的な仕組みは、うまく使えばアプリやサービスのモチベーションブースターになります。
たとえば:
学習アプリ → 「問題を解くとランダムでスタンプゲット」
健康アプリ → 「1日続けるとランダムでアイテム」
買い物アプリ → 「購入ごとに抽選ポイント」
「確実な報酬」だけでなく、「たまにうれしいサプライズ」があることで、
人は“もう一度やってみよう”という気持ちになります。
注意点:依存と期待のコントロール
ただし、ガチャには強力な引力があるため、設計のバランスが非常に重要です。
当たり率が低すぎると、やる気を失う
逆に報酬が強すぎると、依存を招く
期待だけ煽ると、信頼を失う
ユーザーが「またやりたい」と感じる適度な緊張感を保つことが理想です。
“ストレスではなく、ドキドキ感”を生む設計が鍵になります。
まとめ
人は「いつもらえるかわからない報酬」に夢中になる
ガチャは「報酬」ではなく「感情体験」をデザインしている
うまく使えば習慣や継続を後押しする
ただし、やりすぎは信頼を失うリスクも
次回は第18回「スタミナ制:なぜ『制限』がある方が遊んでしまうのか」。
「制限があるほど熱中してしまう」という逆説的な設計の秘密を解き明かします。
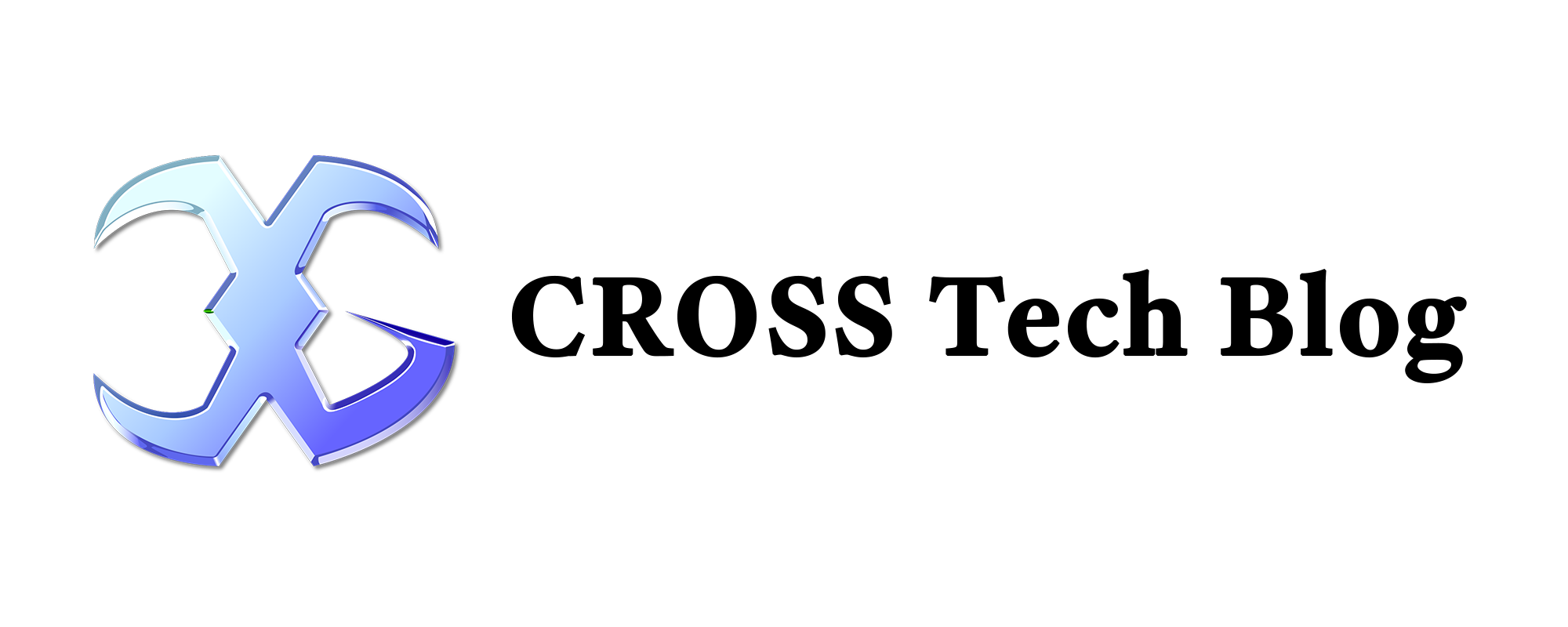



コメント