昔のキャンペーンといえば「抽選で○○が当たる」「○○円以上で応募できる」といった単発型のものが主流でした。
しかし、最近の企業キャンペーンはそれだけでは終わりません。
買い物や来店、SNS投稿などの行動自体に「遊びの要素」を取り入れ、ユーザーが「もっと参加したい」「また試したい」と感じる設計が増えています。
たとえば──
コンビニで買うたびにポイントがたまり「ガチャ」が回せるキャンペーン
SNSで投稿すると“ミッション達成”としてバッジがもらえる企画
ARカメラでキャラクターを探す“リアル探索ゲーム”型イベント
これらはすべて「買う」や「投稿する」といった行動に、ゲームのような報酬や達成感を付与した例です。
“参加したくなる”心理をどう作るか
人は単に「割引」よりも、「チャレンジ」や「特別な体験」に惹かれやすいものです。
「抽選で当たる」よりも、「ミッションをクリアしてチャンスを得る」と言われると、自然と行動したくなります。
これは心理学でいう「自己決定理論」とも関係があります。
自分の行動が「選んだ」「挑戦した」と感じられると、満足度が高まるのです。
つまり、キャンペーン設計では「買わせる」より「参加したくなる」構造を作ることが重要です。
成功しているキャンペーンの共通点
人気のあるゲーミフィケーション型キャンペーンには、いくつかの共通点があります。
目標が明確で短期的(“今日やる”理由がある)
達成すると報酬がある(抽選、限定特典、SNSバッジなど)
進捗が見える(メーターやポイント、スタンプ)
共有したくなる(SNS投稿やランキング要素)
この4つを意識すると、単なる販促企画が「体験型マーケティング」に変わります。
日常の中の“楽しい”をデザインする
たとえば、
「○日連続で来店したらレアバッジを贈呈」
「特定商品のQRコードをスキャンしてポイントを貯める」
「友達を招待してチームで達成率を競う」
などは、どれも“遊びながら買う・関わる”体験を作り出します。
ユーザーにとっては“ちょっとした遊び”でも、企業にとっては自然なリピートと拡散の仕掛けになります。
まとめ
これからのマーケティングでは、「買ってもらう」よりも「一緒に楽しむ」設計が鍵になります。
ユーザーが物語の登場人物のように参加できるキャンペーンこそが、次の時代のブランド体験です。
次回(第26回)は、
「習慣づくり(ダイエットや家計簿)に応用する」
——日常生活の中で“ゲームの力”を活かす方法について掘り下げます。
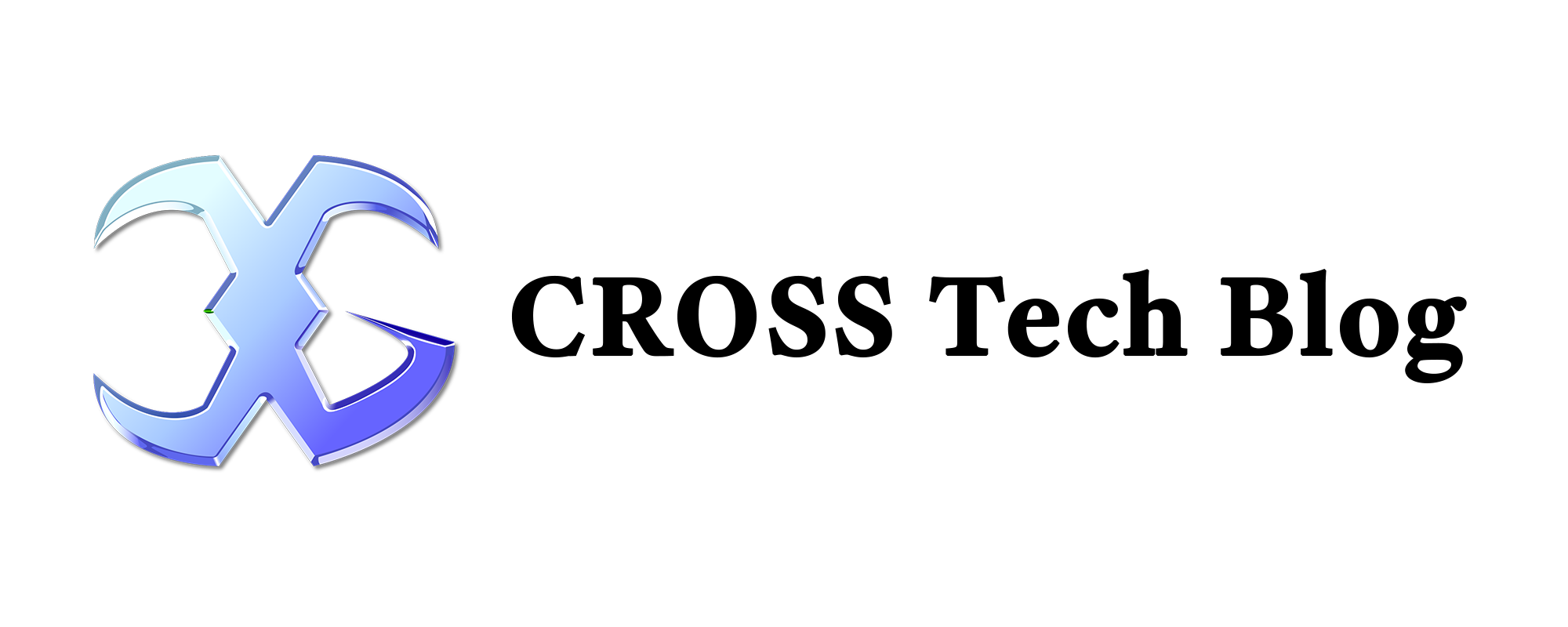



コメント