多くの企業が抱える悩みのひとつに、
「研修が退屈で身につかない」という問題があります。
受講しても記憶に残らない
モチベーションが続かない
参加者が“受け身”になりがち
これを変えるのが、ゲーミフィケーションによる研修設計です。
学びや評価の仕組みに“ゲームの楽しさ”を取り入れることで、
社員が“自ら動く”研修体験を生み出せます。
「学び × ゲーム」の代表的な仕組み
| ゲーム的仕掛け | 社内研修での例 | 狙い・心理効果 |
| 🎯 ミッション形式 | 「今日の課題をクリアしよう」 | 学習目標の明確化 |
| 📈 レベルアップ | 習熟度に応じてレベル上昇 | 成長の可視化・達成感 |
| 🏅 バッジ・称号 | 「認定リーダー」「応用修了バッジ」 | 承認・モチベーション向上 |
| 🧠 クイズ・シナリオ形式 | 選択肢を選んで進む学習 | 参加意欲の維持 |
| 🤝 チーム戦 | 部署対抗・同期対抗チャレンジ | 協力・競争意識の促進 |
| 🎁 ごほうび | ポイント・評価・景品など | 行動の強化・継続化 |
たとえば「コンプライアンス研修」や「新入社員教育」など、
堅いテーマほど“ゲーム的構造”が効果的に機能します。
学習の仕組みは「ごほうび」より「達成感」
研修のモチベーションを上げるために、
単純にポイントや報酬を与えるだけでは不十分です。
本当に大切なのは、「自分が成長している」と感じられる瞬間。
レベルアップやスキルツリーで、学習の進歩が見える
過去の自分より“理解度が上がっている”ことがわかる
これらが「学びの内的報酬」となり、
社員の“自発的な成長意欲”を引き出します。
実例:ゲーミフィケーション研修の導入事例
💡 例1:日本マイクロソフト
セキュリティ教育にクイズ形式を導入
チームごとの得点を競わせる仕組みで参加率アップ
受講者満足度が前年比約40%向上
💡 例2:Salesforce(海外)
社員トレーニングプラットフォーム「Trailhead」を導入
学習すると“トレイルバッジ”がもらえ、称号が可視化
スキル習得が“冒険ゲーム”のように進行
💡 例3:国内企業(例:リクルート・トヨタ)
OJTの進捗をレベル形式で管理
部署ごとに“経験ミッション”を設定
目標達成が可視化され、上司・部下間のコミュニケーションも活発に
心理効果①:競争と協力のバランス
ゲーミフィケーション研修では、
「個人の競争」だけでなく「チームの協力」を同時に設計することが重要です。
競争だけだと疲弊しますが、
協力を取り入れることで“共に学ぶ楽しさ”が生まれます。
ゲームでも“レイド戦”や“協力プレイ”が人気なように、
社員教育でも「一緒に成長する体験」がモチベーションになります。
心理効果②:「進捗が見えると続けたくなる」
従来の研修は、「受けた/受けてない」だけで終わりがちでした。
しかし、進捗を数値化・視覚化することで、
自分の学びを“積み上げていく感覚”が生まれます。
「あと2つで修了バッジがもらえる」
「チーム全員がレベル5を達成した」
こうした“あと少し”の設計が、自然な学習継続を生みます。
心理効果③:「上司からの承認がごほうびになる」
ゲームのバッジがうれしいのは、
“誰かに認められる”から。
研修も同じで、
「○○さん、応用課程クリアおめでとう!」と
社内SNSや朝礼で称賛されるだけで、
行動意欲は大きく変わります。
これは心理学でいう「社会的承認」に基づく報酬です。
モチベーションの根源は“褒められる”ことにあります。
ポイント:強制ではなく「選べる」設計に
ゲーミフィケーション研修を成功させるコツは、
「やらされている」から「自分で選んでやっている」状態に変えること。
自分でテーマを選べる
興味ある順にチャレンジできる
難易度を調整できる
こうした“プレイヤーの自由度”が、
自発的な参加を生み出す鍵になります。
応用例:日常の学びにも使える設計
| シーン | 応用例 |
| 社内研修 | ミッション式・スコア表示 |
| 営業トレーニング | 成績でバッジ付与・社内称号 |
| eラーニング | クイズ形式・シナリオ学習 |
| チーム育成 | 協力ミッション・進捗共有 |
研修を「一方通行」から「体験型」に変えることで、
社員が“学ぶことそのもの”に前向きになります。
まとめ
ゲーミフィケーションは「学びを自分ごと化」する力を持つ
レベル・バッジ・協力プレイで、モチベーションが循環
強制よりも「選択と達成感」を重視することで定着率が向上
次回は第25回「マーケティングやキャンペーンのゲーミフィケーション」。
“買いたくなる・参加したくなる”仕掛けはどう作られているのか?
企業が顧客を動かすための心理設計を解説します。
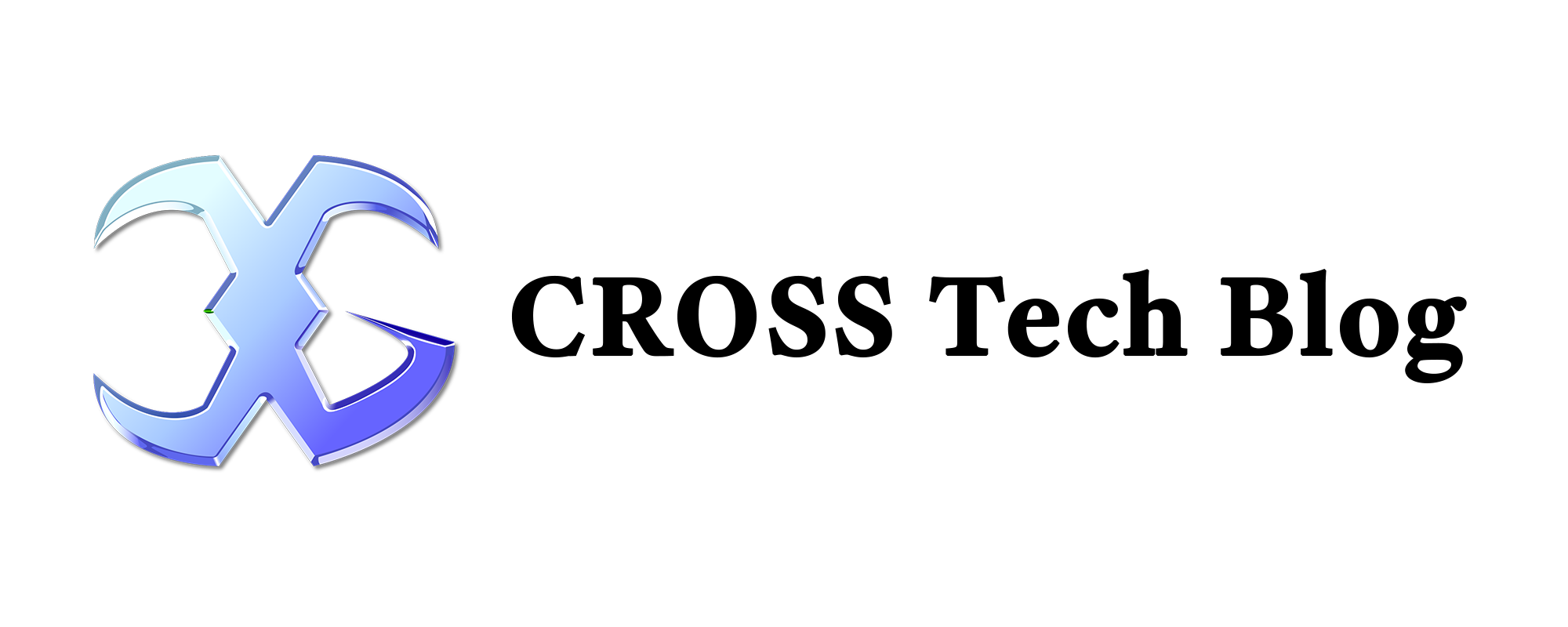
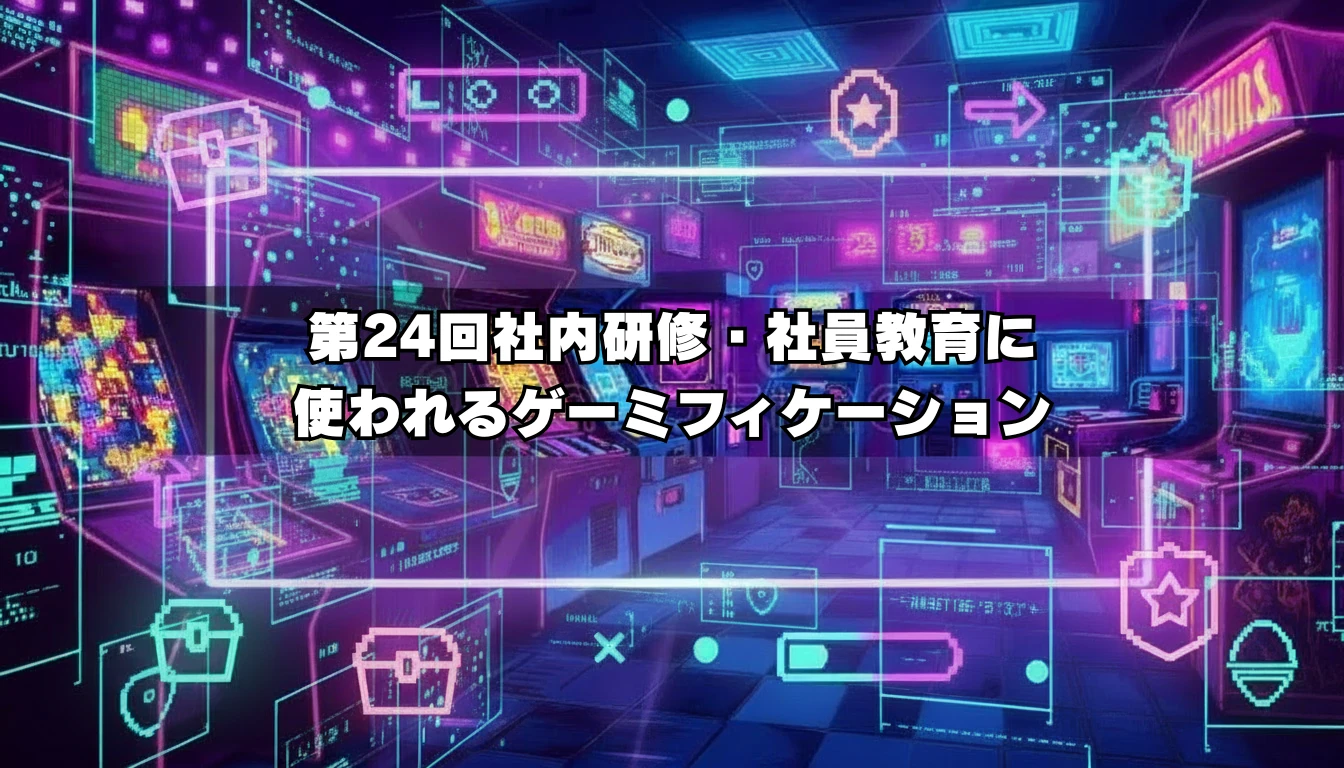


コメント